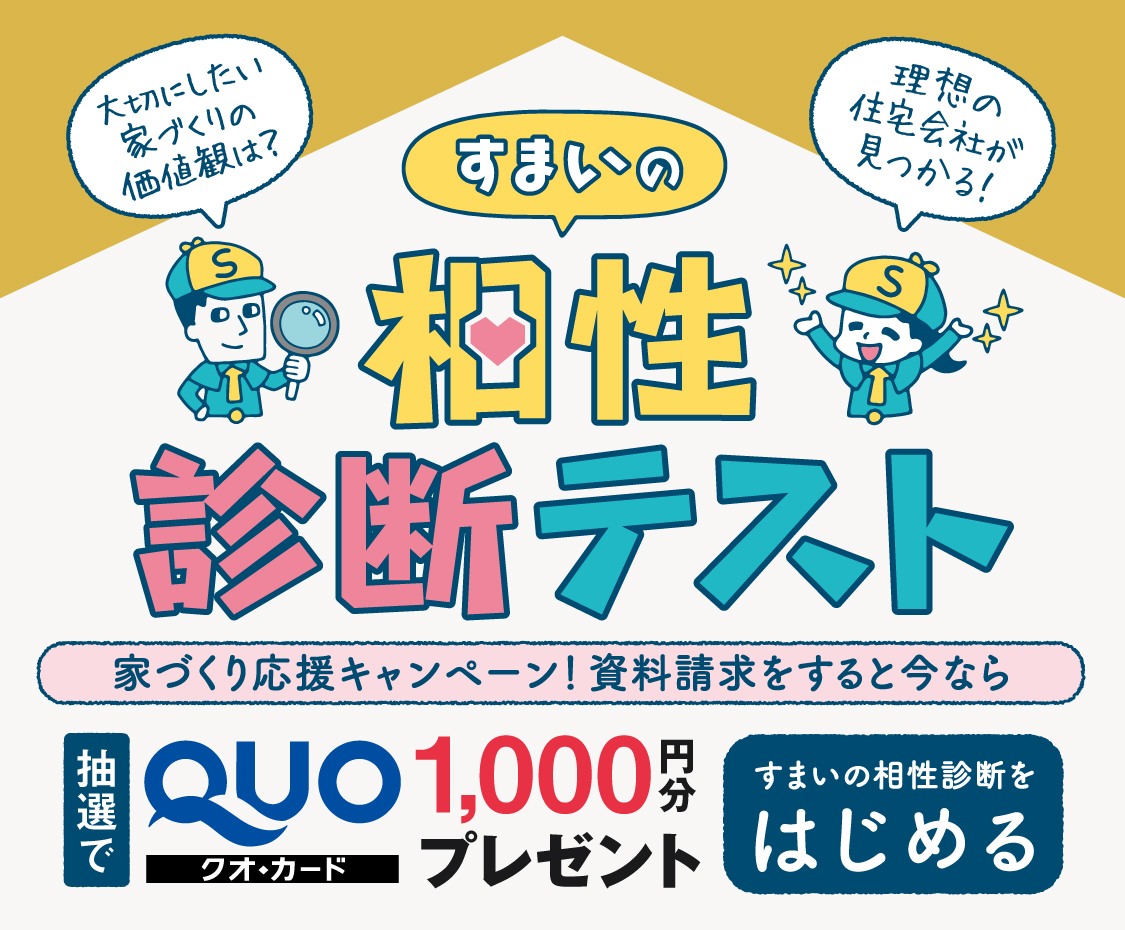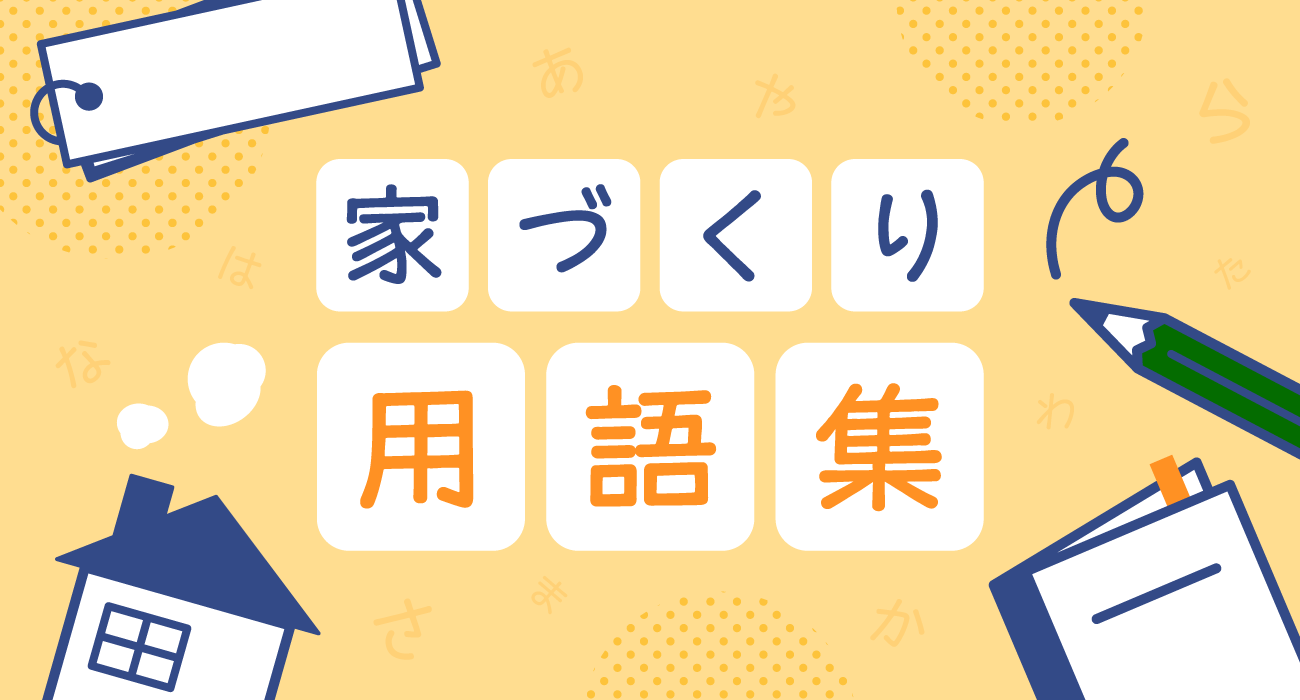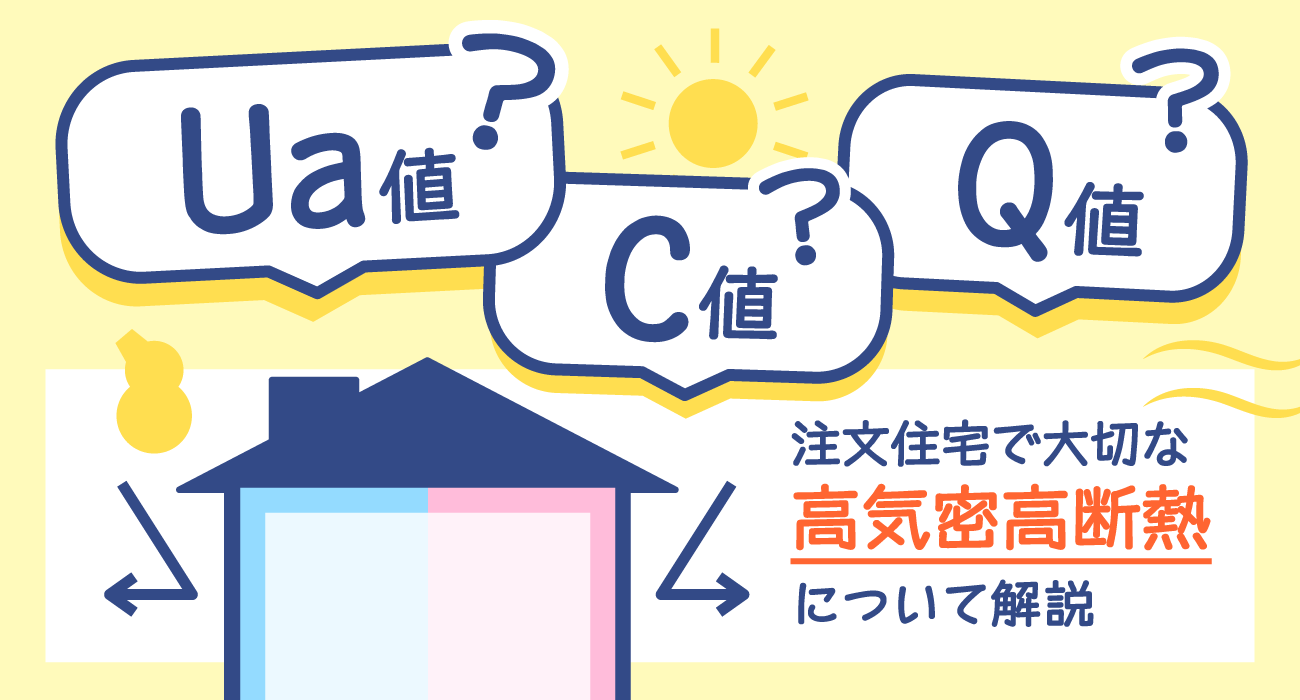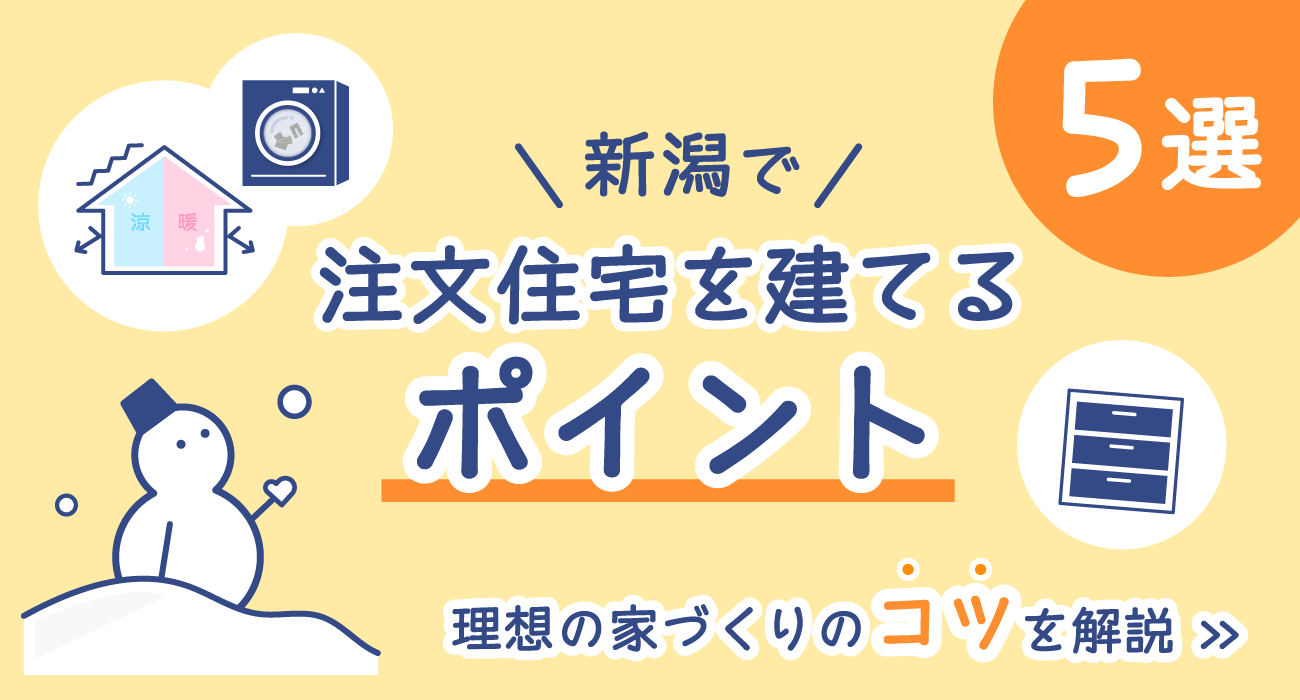新潟県で狭小住宅に住むメリットは?デメリットと後悔しないための工夫
利便性を優先したいときや、予算の関係で土地購入にあまり費用をかけられないときに挙がるのが、“コンパクトな土地の購入”と“狭小住宅”だと思います。
しかし「狭小住宅は暮らしにくそう」「後悔するかも」と不安に思っている方も多いはずです。
マイナスなイメージを抱きがちな狭小住宅ですが、実際は費用面や暮らしやすさにさまざまなメリットがあります。
しかしその一方でデメリットもあるため、自分たちのライフスタイルや価値観が合うのかを、慎重に考えなければなりません。
そこで今回のコラムでは、狭小住宅を建てる前に知っておきたいメリットとデメリット、暮らしを快適にするために意識すべきポイントを解説します。
ぜひ参考にしてください。
そもそも「狭小住宅」とは?
狭小住宅に明確な定義はありませんが、一般的には“敷地面積が15坪(約50㎡)以下の土地に建てられた住宅”を指します。
建ぺい率や容積率によっても変わりますが、多くの場合、延べ床面積は20坪以下になります。
狭小住宅と混同されやすいものに「コンパクトハウス」がありますが、こちらは敷地面積に限らず床面積が30坪未満の住宅を指すので、敷地の条件が異なります。
新潟県で狭小住宅を選ぶメリット

冒頭でもお伝えしたように、狭小住宅はマイナスなイメージを抱かれることが多く、検索すると「後悔」「恥ずかしい」などのネガティブな言葉が出てくるので不安になるかもしれません。
しかし狭小住宅には、多くのメリットがあります。
建築費用を抑えられる
注文住宅を建てるときには『坪単価(1坪あたりの建築費用)』によってベースとなる金額が決まるため、床面積が広くなるほど費用も高くなっていきます。
たとえば坪単価が100万円の住宅会社で床面積が35坪の家を建てるのなら、費用の目安は3,500万円です。
一方で狭小住宅は20坪以下になることが多いので、同条件なら建築費用は2,000万円と、一般的な住宅よりも費用を大きく抑えられます。
これが、狭小住宅を建てる大きなメリットです。
ただし、敷地の前面道路が狭いと資材運びや管理などにとても手間がかかるため、工事費用も高くなります。
付帯工事の有無は、事前に必ず確認しておきましょう。
立地を優先できる
狭小住宅ならばこれらの好立地でも土地購入費用を抑えられるので、立地を優先できる点がメリットです。
新潟市中心部や駅周辺エリアのように地価が高い場所でも、狭小地ならば予算内で購入できる可能性があります。
また、利便性がよい土地は資産価値も高いので、万が一売却することになった際にも有利に売却を進められるでしょう。
光熱費を抑えられる
光熱費が年々上昇しており、冬に厳しい寒さが続く新潟県ではとくに暖房費が家計に大きな負担となっているはずです。
しかし狭小住宅ならば暖房を効かせる範囲が狭いので、一般的な住宅と比べて光熱費を抑えられます。
さらに高気密高断熱住宅にすれば、少ない電力で室内全体の温度を保ちやすいので、一年を通して快適な住まいになるでしょう。
税負担を軽減できる
固定資産税や土地や建物を取得したときに納める『登録免許税』は、敷地面積や住宅の床面積をもとに算出されます。
評価基準は面積だけではありませんが、広い土地や家は“資産価値が高い”と判断され、固定資産税と登録免許税も高くなる傾向があります。
一方で狭小住宅は土地も建物面積もコンパクトなので、一般的な住宅よりも税負担を抑えられる場合がほとんど。
長く住み続けることを考えると、税負担が抑えられるのは狭小住宅を選ぶ大きなメリットと言えます。
新潟県で狭小住宅を選ぶときに知っておくべきデメリット

狭小住宅にはさまざまなメリットがありますが、知っておくべきデメリットもいくつかあります。
プランニングが難しい
狭小住宅では、限られた空間を有効活用するための細やかな配慮と緻密な設計が求められます。
とくに新潟県では、雪対策のための設備配置や冬期間の室内干しスペースの確保など、住みやすさ以外の要素も考慮しなければなりません。
これらが考慮されていなければ、住み始めてから狭さや不便さを感じるでしょう。
限られた面積を有効活用し、快適に暮らせる住まいを実現するためには、狭小住宅の対応実績があり、自由設計に対応している会社を選ぶのが安心です。
動線計画が難しい
狭小住宅はコンパクトがゆえに動線が重なりやすく、朝の忙しい時間帯に洗面室やトイレに人が集中しがちです。
そのため家族全員の外出が同じタイミングになる家庭だと、思うように身支度が進まず、ストレスに感じてしまうかもしれません。
対策としては、家族のライフスタイルや家の中の動きに合わせて水まわり設備を配置する方法や、2階や3階に小さな洗面台を設ける方法があります。
しかしその際には他の部屋との兼ね合いも考えなければならないため、緻密な設計が求められます。
このような動線計画の難しさが、「狭小住宅は後悔する」「計画が難しい」と言われる大きな理由です。
維持費が高くなりやすい
狭小住宅で見落としがちなのが、建てた後の維持費です。
狭小地でのリフォームは作業負担が重いため、新築時と同じように付帯工事によってリフォーム費用が高くなる可能性があります。
戸建住宅は10〜15年おきに外壁や屋根のリフォームが必要になりますが、新潟県では雪による建物への負担が大きいため、建物・雪止め・雨どいの点検など雪国特有のメンテナンスも欠かせません。
しかしその都度追加料金が必要になると、結果的に大金を支払うことになります。
維持費を少しでも抑えるためには、メンテナンス頻度が低く耐久性にも優れている外壁材と屋根材を選ぶのがポイントです。
たとえばガルバリウム鋼板は耐用年数は20〜30年、メンテナンスも15年〜20年と長いので、他の素材と比べてメンテナンス費用を抑えられます。
初期費用だけにとらわれず、メンテナンスも含めて素材を選びましょう。
狭小住宅が向いているのはこんな人

メリットやデメリットを見ただけでは、「自分が狭小住宅に合うのかわからない」と感じた方も多いでしょう。
最後に、狭小住宅に向いている人の特徴を説明します。
土地の利便性を優先したい人
家の広さよりも立地を優先したい人は、狭小住宅に向いています。
とくに通勤や通学で毎日公共交通機関を利用する人や、車の運転が苦手な人などにとってはなおさらです。
広さと立地を天秤にかけたときに、立地のほうに重きを置きたいと考える方は、狭小住宅を視野に入れるとよいでしょう。
コンパクトな暮らしをしたい人
物を持ちすぎず、シンプルな暮らしをしたいと考える人には狭小住宅が最適です。
無駄を省いた住まいはとてもスッキリしているのはもちろん、掃除や片づけをする範囲が小さく家事負担をぐっと軽減できます。
とくに新潟県では冬期間は家で過ごす時間が増えるので、自分たちが心地よいと思える空間づくりがとても大切です。
マイホーム費用を抑えたい人
無理なく返済できる額で住宅ローンを組みたいと考えている人にも、狭小住宅が向いています。
狭小住宅は仕様によっては一般的な注文住宅よりも1,000万円近く費用を抑えられる可能性があるので、住宅ローンの返済負担の軽減によって家計にゆとりができ、住宅ローン破綻のリスク対策にもなります。
無理なく返済できる額でマイホームを実現できるのも、狭小住宅の魅力のひとつと言えそうです。
まとめ

建築費の高騰や住宅ローン金利の上昇、そしてコスパ(コストパフォーマンス)やタイパ(タイムパフォーマンス)が重視されるなどの価値観の変化によって、狭小住宅もマイホーム計画の選択肢に挙がるようになりました。
今回お伝えしたように狭小住宅には費用面や暮らし面においてさまざまなメリットがありますが、その一方で見過ごせないデメリットも存在します。
その部分に目をつぶってしまうと後悔する恐れがあるため、「本当に自分たちに合っているのか」をよく話し合ってみてください。
狭小住宅を計画するときの具体的な対策方法や不安点については、住宅会社に相談してから決めるのが安心です。
そして住宅会社選びの際にはぜひ、sumicaのすまいの相性診断テストをご活用ください。
診断結果に応じておすすめできる複数の会社へ、一括で資料請求や相談の問い合わせができます。
(監修/(株)新潟家守舎)