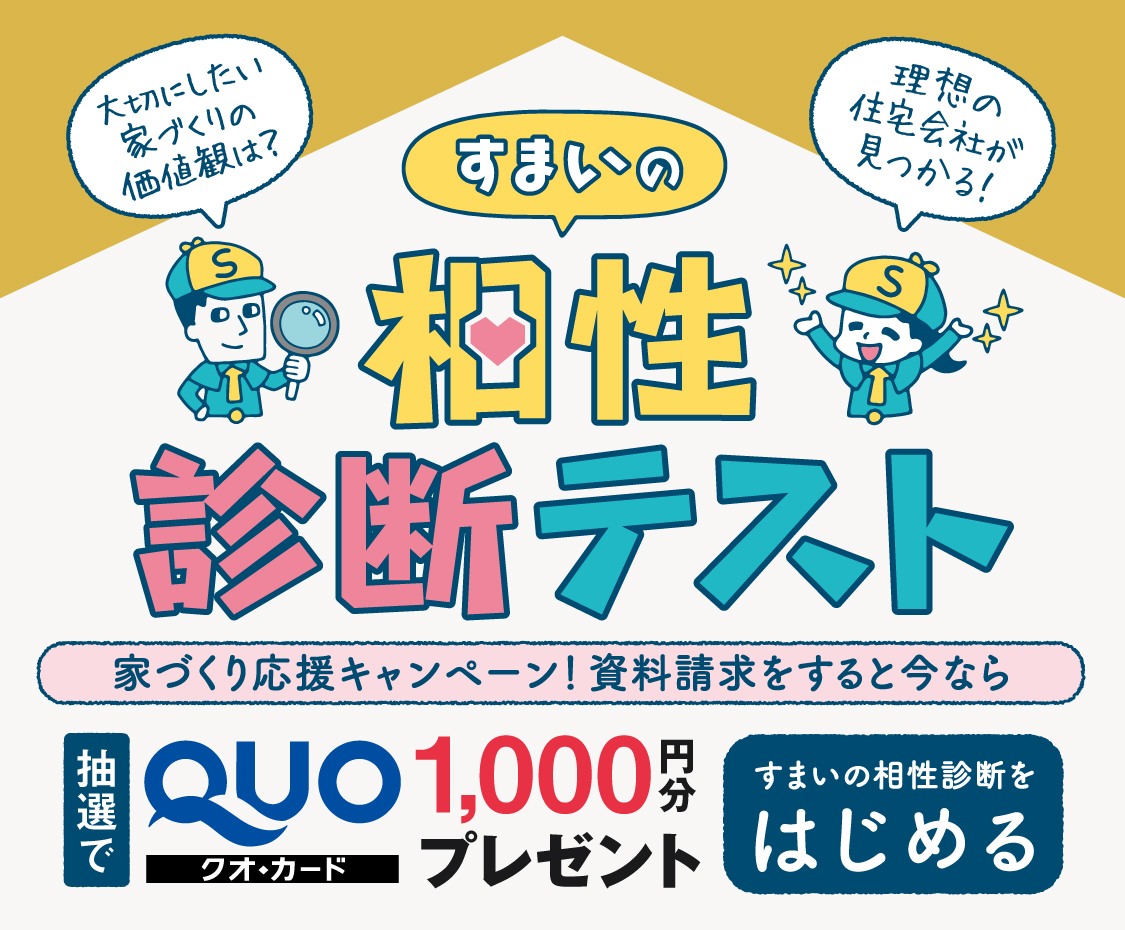新潟県で注文住宅を建てるときに必要な広さは?床面積を決めるポイント
注文住宅の魅力は、なんといっても希望の間取りを決められることです。
しかし家が広すぎると持て余してしまうし、狭いと快適な生活ができないので、「自分たちにちょうどいい広さって、どのくらいだろう?」と悩んでしまう方も多いでしょう。
家の広さは、家族構成や世帯人数、予算、土地の条件などのさまざまな観点から考えていきます。
そこで今回のコラムでは“注文住宅の広さ”をテーマに、平均値や決めるときのポイントを説明します。
坪数別の間取りイメージなどもお伝えしますので、ぜひ参考にしてください。

注文住宅の広さで悩んだときには、平均値を参考にするのがおすすめです。
ここでは家づくりの基本である、注文住宅の広さを示す指標と、平均的な広さを説明します。
注文住宅で“広さ”を示す指標
注文住宅の面積を表現するときには、次の3つの指標が使われます。
● 坪
● 畳
● 平米(㎡)
土地や家全体の床面積を表すときには「坪」、部屋の広さを表すときには「畳」や「平米(㎡)」が使われるのが一般的です。
3つの単位を整理すると、“1坪 = 約2畳 = 3.30579平米(㎡)”となります。
広さごとの単位も見てみましょう。
● 10坪 = 約20畳 = 約33.05平米(㎡)
● 20坪 = 約40畳 = 約66.11平米(㎡)
● 30坪 = 約60畳 = 約99.17平米(㎡)
畳の大きさに関しては地域や工務店、ハウスメーカーによって若干異なりますが、新潟では「五八間(江戸間)」が一般的なので、サイズは約176cm × 88cmになります。
これらの単位は打ち合わせを進める中で何度も出てくるので、それぞれの大きさをイメージできるようにしておきましょう。
全国・地域別の注文住宅の平均的な広さ
続いて、住宅金融支援機構が発表した「フラット35利用者調査」の結果をもとに、2023年(令和5年)に土地を購入して注文住宅を建てた人の平均的な家の広さを見てみましょう。
ここでは全国平均と、新潟県に隣接する県の平均値を挙げていきます。
表を見ると、どの地域でも30〜35坪あたりが注文住宅の平均的な広さだと分かります。
ただし上記はあくまで平均値なので、新潟県内であっても地価が高い新潟市や長岡市などの都市部では、30坪以下の住宅も少なくありません。
逆に地価が安い郊外や山間部にいくと、40坪を超える住宅も多くあります。
このように、土地の価格や面積によっても家の広さは変わってくるので、30坪前後をベースに、自分たちに必要な広さを考えていくのがおすすめです。
参考:住宅金融支援機構「フラット35利用者調査」

注文住宅の広さの平均値は30坪前後だとわかりましたが、いざ自分たちの家の広さを決めるときには、どのような部分から考えていけばよいのでしょうか。
4つのポイントを説明します。
【ポイント①】家族構成や世帯人数から考える
家族構成や世帯人数は、家の広さを決めるときに重要な要素のひとつです。
人数ごとに必要な広さの目安を見てみましょう。
● 夫婦2人:25~30坪
● 家族3~4人:30~40坪
● 親と同居:40~50坪
上記よりも人数が増えるときには、1人につき5〜7坪ずつ面積を増やしていきます。
もし将来的に同居家族が増える可能性があるのなら、面積を増やすのではなく、間仕切りで部屋を増やせるような、可変性のある間取りにするのも一案です。
【ポイント②】予算から考える
注文住宅の建築費用は家の広さをベースに決まり、1坪あたりの施工費用は『坪単価』といって、60〜120万円が一般的です。
これを予算から逆算すれば、予算内で建てられるおおよその広さを計算できます。
たとえば予算が3,000万円なら、坪単価が100万円の住宅会社で建てられる家の広さは30坪前後が目安です。
ただし、坪単価はあくまでベースとなる金額なので、内装材や設備類にこだわると、費用がどんどん上がっていくため注意しましょう。
【ポイント③】土地の条件から考える
宅地に家を建てるときにはさまざまな条件があり、家の面積に影響するのが「建ぺい率」と「容積率」の2つです。
建ぺい率は“敷地面積に対する建築面積の割合”を指し、容積率は“建物の床面積の敷地面積に対する割合”を指します。
たとえば敷地面積が50坪で建ぺい率50%、容積率100%なら、建築面積は25坪、床面積は50坪が上限となり、それを超える家は建てられません。
敷地の面積によって、家の広さが必然的に決まることも頭に入れておきましょう。
【ポイント④】平均値から考える
家の広さで悩んだときには、ひとまず平均値を目安に間取りを組み立てていくのがおすすめです。
前章で説明したように、30〜35坪あたりをベースにして、そこからLDKや各部屋の広さを決めていきながら、自分たちに必要な広さになるよう調整するとよいでしょう。

漠然と広さについて説明されても、その家がどんな住み心地なのかは、なかなかイメージできないと思います。
最後に広さが20〜40坪の家のイメージを説明しますので、自分たちの暮らしに合う広さを考えるヒントにしてください。
20坪前後の家のイメージ
国土交通省が指示する「一般型誘導居住面積水準」では、4人家族がゆとりをもって暮らせる広さは約37.5坪(125㎡)としているため、20坪の家はかなりコンパクトです。
間取りイメージは、LDK18〜20畳、主寝室8畳、子ども部屋6畳くらいになります。
ただし、LDKや個室を小さくしたり廊下に役割を持たせたりするなどの工夫をすれば、快適な暮らしを実現できるでしょう。
施工面積が小さくなる分、建築費用を抑えられるのもメリットです。
30坪前後の間取りイメージ
注文住宅の平均値でもある30坪の家は、3〜4人家族に理想的な広さです。
間取りイメージは、LDK24〜28畳、主寝室8〜10畳、子ども部屋6畳 × 2室くらいになります。
各部屋の広さによっては書斎や納戸を設けることも可能です。
30坪の広さがあれば各部屋の広さと収納スペースを十分に確保できるので、生活の利便性がぐっと上がります。
家の面積と建築費用のバランスがよく、ライフスタイルの変化にも対応しやすい広さと言えるでしょう。
40坪前後の間取りイメージ
40坪の家は、4〜5人家族なら空間にかなりゆとりがあり、親との同居もできる広さになります。
イメージとしては、LDK20〜24畳、和室8畳、主寝室8〜10畳、子ども部屋6〜8畳 × 3室ほどです。
ほかにも、ランドリースペースやファミリークローゼットを設けるゆとりもあります。
ただし坪数が増える分、建築費用も高くなるため、仮に坪単価が100万円なら建築費用のみで4,000万円を超えるでしょう。

注文住宅の床面積の目安は、30〜35坪ほどです。
しかし家は広ければいいというわけではなく、最近では建築費用を抑えるために、無駄を省いたコンパクトな家を建てる人も増えています。
予算内で満足度が高い家を建てるためには、自分たちに合う広さを家族でよく話し合うことが大切です。
しかしその際には、家づくりの専門家である住宅会社のアドバイスにも耳を傾けてみてください。
ヒアリングをもとに、自分たちに必要な広さを提案してもらえるはずです。
そして住宅会社選びの際にはぜひ、sumicaの相性診断テストをご活用ください。
診断結果に応じておすすめできる複数の会社へ、一括で資料請求や相談の問い合わせができます。
(監修/(株)新潟家守舎)