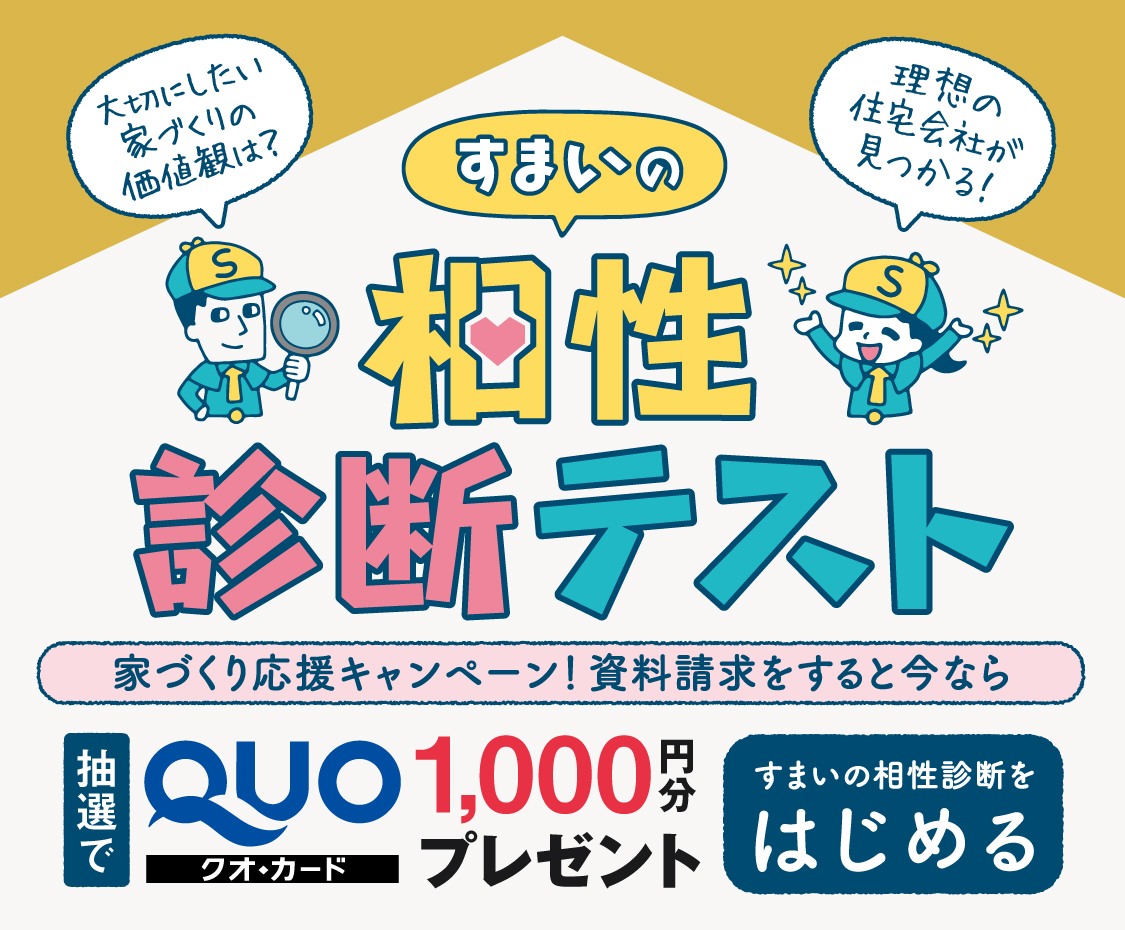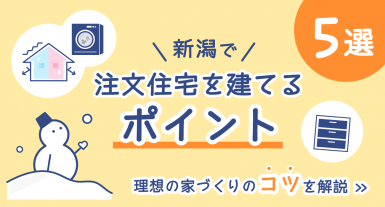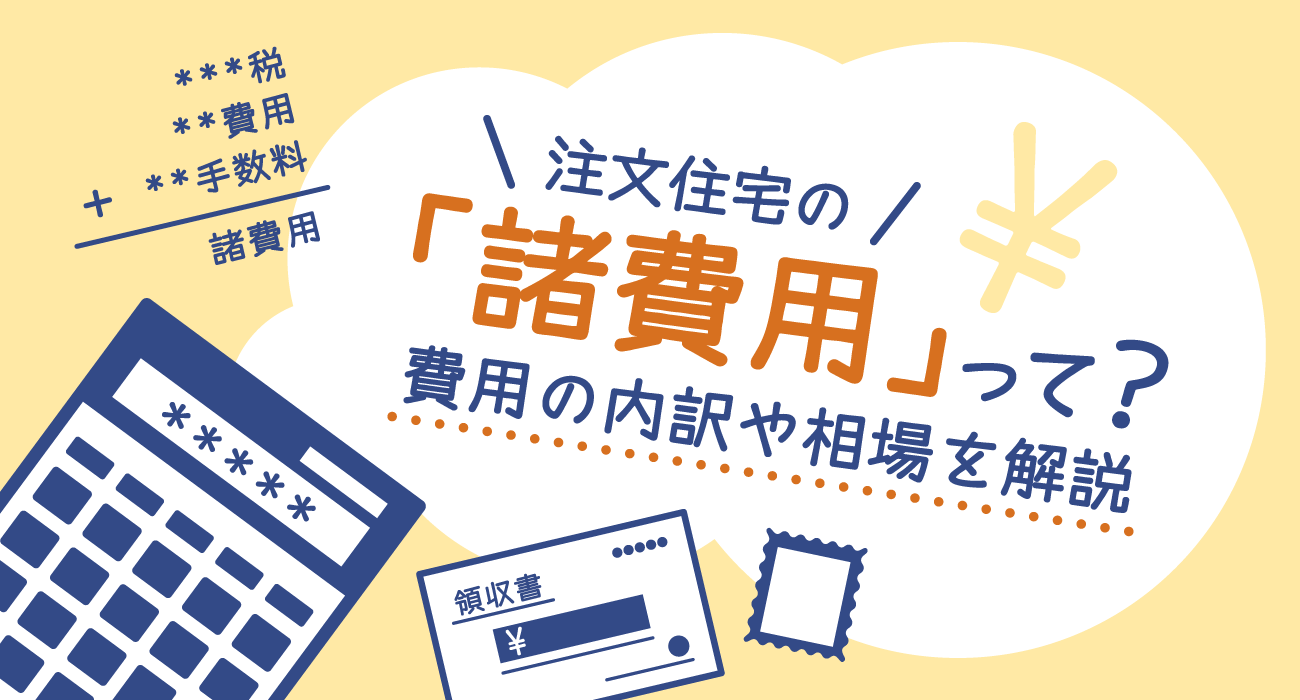
注文住宅の「諸費用」とは?費用の内訳や相場を解説
注文住宅にかかる費用には、土地や建物以外に「諸費用」があります。
しかし見積書ではひとまとめにされていることも多く、その内訳に疑問を持つ方もいらっしゃるのではないでしょうか。
そこで今回は、注文住宅における諸費用の内訳、そして諸費用がいくらくらいかかるのかの相場感について解説します。
諸費用を抑える方法についてもご紹介していますので、ぜひ最後までお読みください。
なお、これから注文住宅を建てようと考えている方は、資金計画の第一歩としてsumicaの住宅ローンシミュレーションをぜひご利用ください。
返済額や借りたい金額を設定して、自分たちの資金や年収であればどの程度の借り入れになるのか目安にすることができます。
シミュレーションのあとには金融機関への相談も可能なので、専門家にサポートしてもらいたい方は、一度こちらを試してみてください。
家づくりにかかる「諸費用」とは?

家づくりにおける「諸費用」とは、土地の購入や設計・施工以外にかかる費用全般のことを指します。
主に様々な申請に関わる手数料や、各種税金などが当てはまります。
注意していただきたいのは、組み込み可能なものを除き、諸費用は住宅ローンで賄えず、自己資金で支払うことです。
自己資金ですべての諸費用を支払うことが難しい場合は、諸費用を建て替える別のローンを組むつなぎ融資というものもありますが、もちろん利息が発生するので、気軽におすすめはできません。
【変動金利の住宅ローン】2種類のタイプに注意 - つなぎ融資とは? | 新潟日報sumica
諸費用は項目によって支払うタイミングも異なるため、ローンの申請や頭金の支払い、資金計画全般ではこの諸費用を考慮することが非常に大切です。
費用相場は総額の5%〜10%
それでは、注文住宅における諸費用はどれくらいかかるのでしょうか?
土地の有無や状況によって異なりますが、一般的に総額の土地・建築費用を合わせた総額の5%〜10%ほどの諸費用がかかるとされています。
例えば、土地の価格が1,000万円、建築費用が3,500万円だった場合、合計した4,500万円の5%〜10%、つまり225万円〜450万円ほどの諸費用が予想されます。
「諸費用」とひとまとめにされていますが、決して安い金額ではありません。
油断せず、しっかりと資金を準備しておきましょう。
「諸費用」と「諸経費」の違い
注文住宅を建てるときによく聞く言葉として、「諸経費」というものがあります。
言葉が似ているため諸費用と混同されがちですが、諸経費は建物を建てる手続き上にかかる費用を指しています。
例えば、設計費用や建築確認申請費用、工事請負契約の印紙代などです。
これらの費用は注文住宅を建てる上で必ずかかる費用で、諸費用の一部として計上されることもあります。
注文住宅にかかる諸費用の内訳

ここからは、諸費用にはどのような項目があるのか、その内訳について解説していきます。
諸費用は土地、建物、住宅ローンそれぞれにまつわるため、この3つに分けて解説していきます。
土地に関する諸費用
土地に関する諸費用は、業者へ支払うものや、税金などがあります。
| 不動産仲介手数料 | 土地を仲介した不動産業者に支払う手数料 |
|---|---|
| 印紙税 | 土地の売買契約書に貼る印紙代 |
| 登録免許税 | 所有権移転登記の際に発生する税金 |
| 司法書士費用 | 所有権移転登記を司法書士に依頼する場合に支払う報酬 |
| 不動産取得税 | 新たに不動産を取得した際に課される税金 |
| 固定資産税・都市計画税 | 土地を購入した際にかかる税金 |
これらの他、必要に応じて解体費用などの費用がかかる場合もあります。
なお、住宅を建てるための土地に関しては税負担を軽減する特例措置が出ている場合もあります。
常に軽減されているとは限りませんし、税率の変更や新たな軽減措置が公布される可能性もあります。
注文住宅を建てる際は、このような情報も積極的に収集していきましょう。
建物に関する諸費用
建物に関する諸費用は、手続きにまつわるものやガス・水道の工事・契約費用、税金などが当てはまります。
| 地盤調査費 | 建築地の地盤の強さを調べるための調査費用 |
|---|---|
| 地盤改良費 | 建築地に地盤改良が必要な場合にかかる工事費用 |
| 印紙税 | 工事請負契約書に貼る印紙代 |
| 確認申請費用 | 建築基準法の要件を満たした建物であることを確認するための申請費用 |
| 各種引込工事費用 | 上下水道、都市ガスなどを引き込む工事費用 |
| 登録免許税 | 建物の登記手続きの際に支払う税金 |
| 水道加入金 | 水道加入時に事業者に支払う費用 |
| 外構工事費用 | 庭やカーポートなど、建物以外の工事費用 |
| 引越し費用 | 新居への引っ越しにかかる費用 |
| その他、地鎮祭や上棟式の費用 | 神主さんへの謝礼や、関係者への差し入れなどの雑費 |
建物に関する諸費用は項目が多く、新規で土地を購入した場合と建て替えの場合でも各費用は大きく変わってきます。
例えば新規に土地を購入した場合は各種インフラの引き込みや契約に関する費用が発生します。
一方建て替えの場合は旧居のインフラを引き継げますが、建築中の仮住まいと新居完成後の2回引っ越しが発生し、仮住まいの家賃も負担となります。
自身の状況と照らし合わせて、どれくらの予算が必要なのかしっかりと見極めましょう。
住宅ローンに関する諸費用
住宅ローンに関する諸費用は、ローン申請に必要な手数料や、加入が必要な保険料などが該当します。
| 事務手数料 | 金融機関が手続きを行う際にかかる費用 |
|---|---|
| 印紙税 | ローンの借入契約書に貼る印紙代 |
| ローン保証料 | 保証会社に依頼する場合に発生 |
| 登記費用 | 住宅ローンを借りる際に行う、抵当権設定登記にかかる費用 |
| 司法書士費用 | 抵当権設定登記を司法書士に依頼した場合に支払う報酬 |
| 火災・地震保険料 | 火災・地震保険の保険料 |
| 団体信用生命保険料 | 団体信用生命保険(団信)の保険料 |
事務手数料は金融機関によって、借入金額に対して一定の割合で変動する「定率型」と、借入金額に関わらず一定の金額がかかる「定額型」の2パターンが一般的です。
その他の項目も状況によって要不要が分かれるので、利用する金融機関や司法書士と確認しておきましょう。
注文住宅の諸費用を抑える3つの方法

場合によっては予想外に負担が大きくなることもある注文住宅の諸費用ですが、これらの金額を抑える方法が、主に3つあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
①仲介手数料不要の土地を探す
注文住宅の諸費用を抑える方法1つ目は、「仲介手数料不要の土地を探す」です。
土地の持ち主との仲介ではなく、不動産会社が直接所有している土地を購入する場合や、建築を依頼する工務店やハウスメーカーが所有している土地で建てる場合などは、仲介手数料が不要になるケースがあります。
土地の仲介手数料は宅建法で上限額が定められており、取引価格によって以下のように定められています。
| 取引価格 | 仲介手数料の上限 |
|---|---|
| 400万円以上 | 取引価格(税抜) ✕ 3% + 6万円 + 消費税 |
| 200万円以上〜400万円以下 | 取引価格(税抜) ✕ 4% +2万円 + 消費税 |
| 200万円以下 | 取引価格(税抜) ✕ 5% + 消費税 |
参照:建設産業・不動産業:宅地建物取引業法関係 - 国土交通省
例えば、700万円の土地を購入した場合の仲介手数料は、2024年6月現在だと最大で29万7,000円になります。
仲介手数料不要の物件であれば、それだけで約30万円の資金に余裕ができることになります。
人気のエリアほど坪単価も高くなり、仲介手数料も比例して高額になるため、希望する建築地によっては仲介手数料不要の土地に絞って探してみるのもよいでしょう。
②住宅ローンの比較検討
注文住宅の諸費用を抑える方法2つ目は、「住宅ローンの比較検討」です。
前述の通り、住宅ローンの諸費用には手数料や保証料、団信保険料などがあります。
これらの項目は住宅ローンによってひとまとめに含まれているものや、それぞれ別途費用として分けられているものがあります。
住宅ローンを検討する際は、金利だけでなくこれら諸費用もよく比較することで、よりお得にローンを組むことができるでしょう。
③補助金や優遇制度を活用する
注文住宅の諸費用を抑える方法3つ目は、「補助金や優遇制度を活用する」です。
土地に関する諸費用でもお伝えしたように、住宅にまつわる各種税金には軽減税率が適用されていることがあります。
例えば2024年6月時点で、新潟県では住宅用地の不動産取得税の減額、新潟市では新築住宅の固定資産税が2分の1になる減税制度があります。
また、住宅の性能にまつわる減税制度もあり、例えばそれぞれが設定した省エネ基準を満たすことで適用される住宅ローン減税や、地域型住宅グリーン化事業などがあります。
これらの補助金や優遇制度をうまく活用した家づくりができれば、なるべく費用を抑えつつ快適に暮らせる注文住宅を建てることができるでしょう。
まとめ
今回は注文住宅にかかる諸費用について解説しました。
注文住宅の家づくりでは建物や土地の価格に目が行きがちですが、これら諸費用も決して安くない金額がかかることが分かりましたね。
後から資金不足に陥ったり、思わぬ経費で理想の家づくりを諦めてしまうことの無いよう、事前の資金計画は諸費用も踏まえてしっかりと組んでください。
なお、資金計画のやり方が分からないという方は、sumicaのローンシュミレーションもぜひ利用してみてください。
返済額や借りたい金額を設定して、自分たちの資金や年収であればどの程度の借り入れになるのか目安にすることができます。
シミュレーションのあとには金融機関への相談も可能なので、専門家にサポートしてもらいたい方は、一度こちらを試してみてください。
(監修/(株)新潟家守舎)