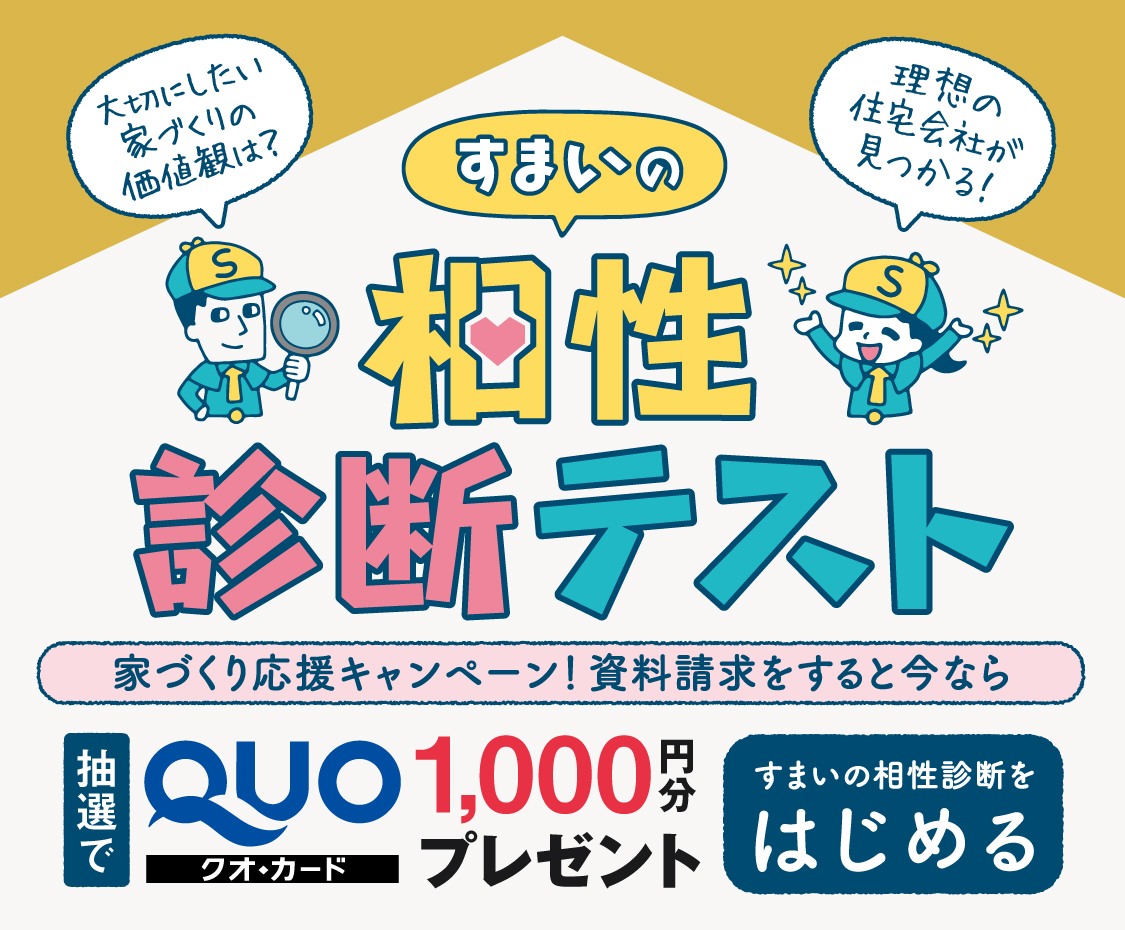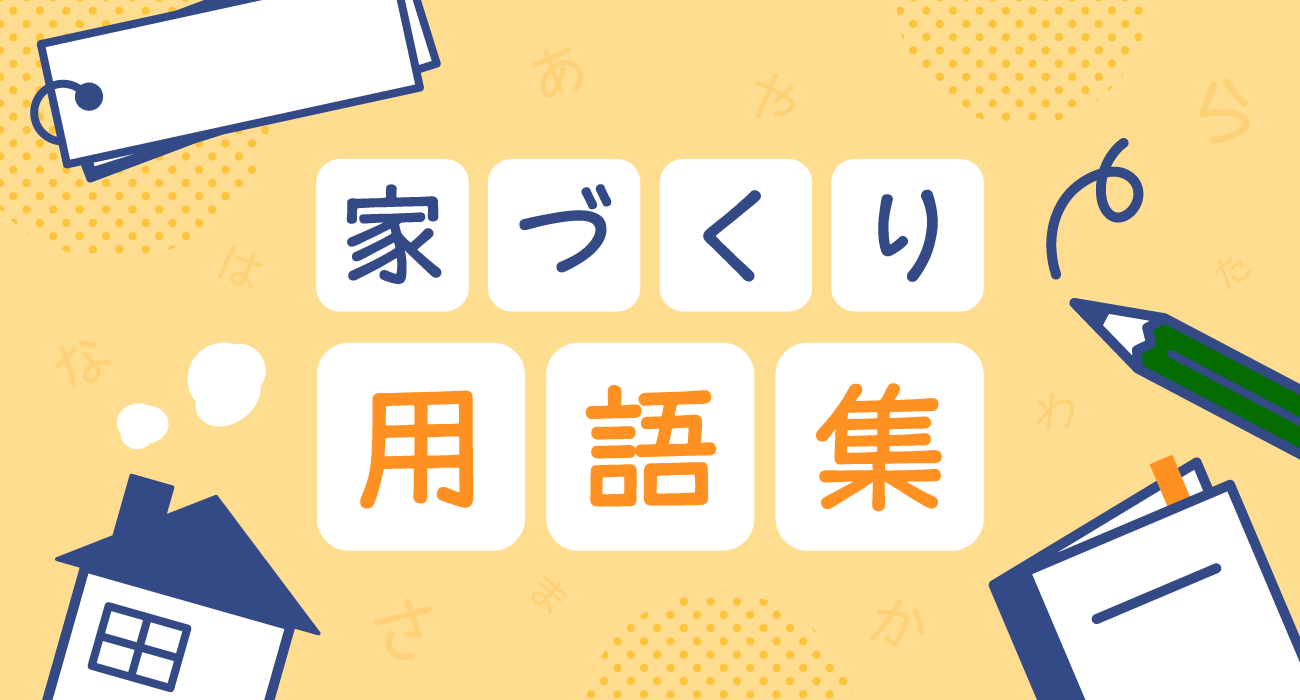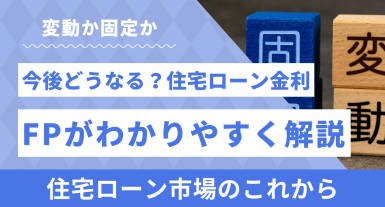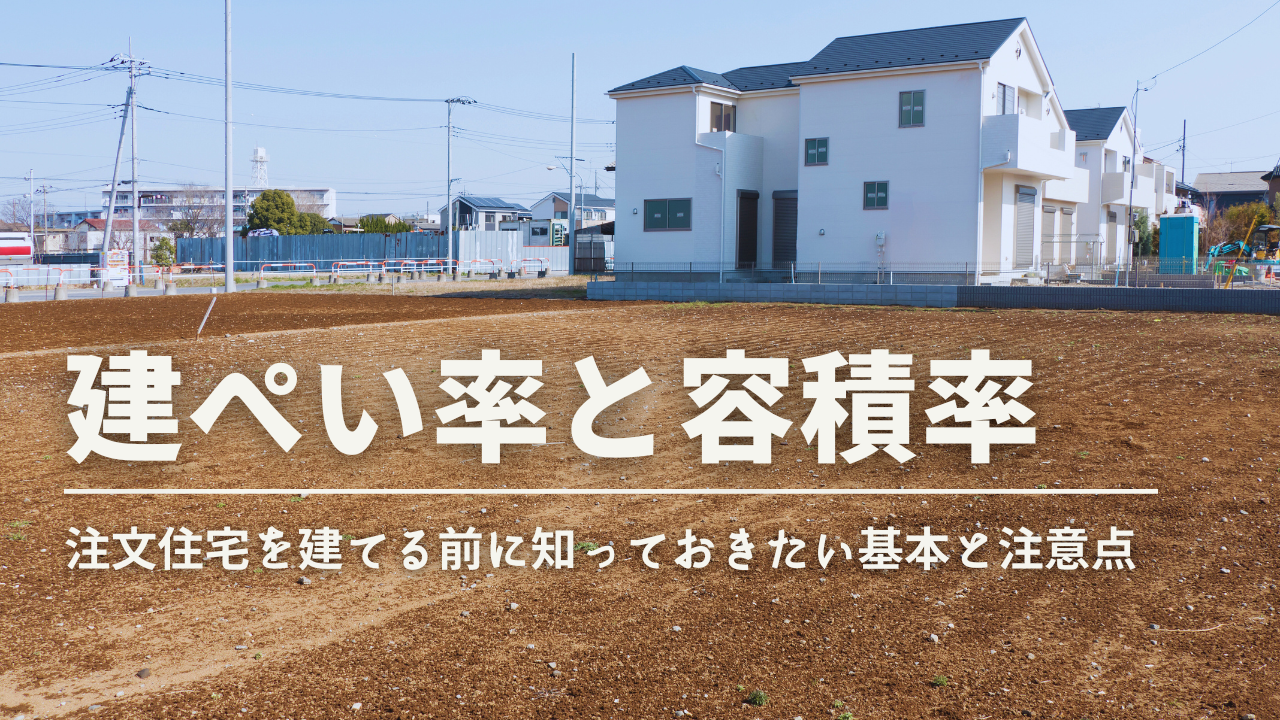
建ぺい率・容積率とは?注文住宅を建てる前に知っておきたい基本と注意点
家を建てるときは、敷地いっぱいに建物を建てられるわけではありません。
決められた「建ぺい率」と「容積率」を守る必要があり、これらを知らずに土地を決めてしまうと、希望どおりの広さの家にできないことも。
とくに雪国である新潟では、雪下ろしや除雪を考えて庭を広く確保したいところです。
そこで本記事では、注文住宅を建てる前に知っておきたい建ぺい率と容積率の基本を解説します。
よくある質問にもお答えしますので、ぜひ土地探しに役立ててください。
「建ぺい率」とは?

建ぺい率は、“敷地面積に対する建物の建築面積の割合”を示す数値です。
ここでいう「建築面積」は、建物を真上からみたときの面積を指します。
新潟では40~60%の間で設定されていることが多く、定められた範囲内でおさまるように建物を建てなければなりません。
なぜこのような制限があるのか、目的と計算方法を見てみましょう。
建ぺい率が設けられている目的
建ぺい率の目的は、住環境に配慮するためです。
建物の面積を制限することで隣家と一定間隔をつくり、火災時の延焼を防ぎ、採光・通風を確保します。
新潟のように広い土地が手に入りやすい地域でも、都市計画によって上限が決められています。
そのため建ぺい率を確認せず土地を決めてしまうと、「思ったより広い家を建てられない」と、後悔することにもなりかねません。
建ぺい率の計算方法
建ぺい率は、以下の計算式で求められます。
・建ぺい率(%)= 建築面積 ÷ 敷地面積 × 100
たとえば敷地面積が250㎡(約76坪)、建ぺい率が50%なら、建築面積は最大125㎡(約37坪)になります。
なお、カーポートや屋根付きの玄関ポーチ、バルコニーのように屋根と柱があるものは、建築物とみなされるため、建築面積に含まれます。
新潟では積雪対策として屋根付きのアプローチや駐車場を選ばれる方が多いですが、建ぺい率に影響する点に注意が必要です。
「容積率」とは?

容積率は、“敷地面積に対する延面積の割合”を示す数値で、住宅各階の床面積を足して算出します。
建ぺい率が平面的な制限であるのに対して、容積率は立体的な制限だと考えれば、イメージしやすいかもしれません。
新潟では50~200%の間で設定されているのが一般的ですが、用途地域によっては200%を超えることもあります。
容積率が設けられている目的
容積率の目的は、建物の規模を制限することです。
建物の大きさを制限することで人口密度をコントロールし、道路の交通量、上下水道、電気などのインフラへの負担を調整しています。
主にマンションやアパートの高層建築の制限が目的ですが、住宅用地にも適用されます。
容積率の計算方法
容積率は次の計算式で求められます。
・容積率(%)=延べ床面積 ÷ 敷地面積 × 100
たとえば敷地面積が敷地面積が100㎡(約30坪)、容積率が100%であれば、延床面積は最大100㎡(約30坪)です。
1階と2階の床面積を合わせての100㎡なので、比較的コンパクトな住宅になります。
容積率は敷地面積にゆとりがあれば問題になりにくいですが、狭小地では「3階建ての住宅ができない」「思ったよりもコンパクトな家しか建てられない」といったケースも。
コンパクトな敷地を買うときは、とくに注意しましょう。
建ぺい率・容積率が家づくりに与える影響

建ぺい率と容積率は、家づくりを進めるなかで次のように影響します。
希望の広さの家が建てられない可能性がある
制限内容を見て「広い土地を買えば安心」と感じた方も多いはずです。
しかし建ぺい率と容積率は敷地条件によって変わってくるので、広い土地を買っておけば安心とは言い切れません。
たとえば、同じように200㎡の敷地でも、建ぺい率が50%か80%かで、建築面積に大きな差が出るからです。
特に平屋は建築面積が大きくなりやすいので、建ぺい率の関係で建てられないことも。
二世帯住宅などで延床面積を広く取りたいときも、容積率の制限によって実現できない可能性があります。
“広い土地=大きな家を建てられる”ではない点に注意しながら、土地探しをしましょう。
場合によっては緩和されることも
建ぺい率と容積率は、条件を満たせば緩和される可能性があります。
主に次のようなケースです。
【建ぺい率】
● 角地:本来の建ぺい率に10%上乗せ
● 防火・準防火地域の耐火建築物:本来の建ぺい率に10%上乗せ
たとえば敷地面積が200㎡(約60坪)、建蔽ぺいが50%の角地なら、+10%になることで120㎡(約36坪)まで建築面積を増やせます。
【容積率】
● 地下室:一定の深さと天井高であれば床面積の1/3まで計算に含まれない
● ビルトインガレージ:床面積の1/5まで計算に含まれない
● ロフト:高さ1.4m以下など条件を満たせば床面積の1/2まで計算に含まれない
このような緩和条件をいかせば、コンパクトな土地でも空間を活用して快適な住まいを実現することができます。
ただし緩和条件は敷地によって異なり、細やかな決まりがあるため、必ず緩和されるとは限りません。
建ぺい率・容積率でよくある質問
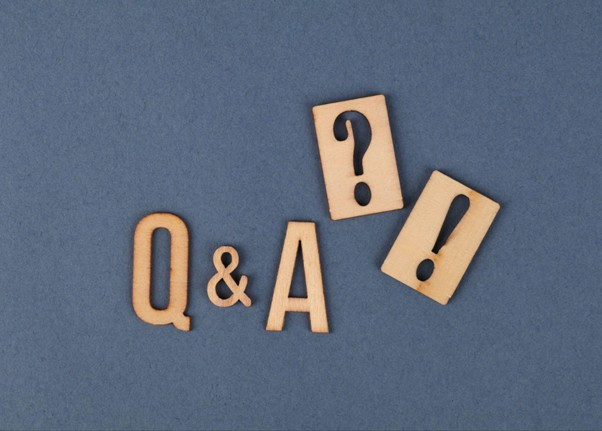
ここまで建ぺい率と容積率の基本を説明してきましたが、それでもいくつか疑問が残っているかと思います。
最後によくある質問にお答えしますので、疑問点をしっかり解消しておきましょう。
Q:制限ギリギリで建てるのはOK?
建築基準法上はOKです。
ただし、ギリギリまで使い切ると後から困りごとが出てくる場合もあります。
● 採光や通風ができない
● 将来的な増築ができない
● 外構(庭、駐車場)スペースが取れない
「なんとか希望どおりの家を建てられる」土地を選ぶのではなく、ゆとりのある土地のほうが安心です。
Q:建て替えだと昔より小さい家しか建てられないって本当?
場合によっては、小さい家しか建てられない可能性があります。
建築基準法が施行された1950年(昭和25年)以前に建てられた住宅を建て替える場合は、セットバックによって既存住宅よりも面積が小さくなるかもしれません。
【セットバックとは?】
建物を建てる際に、土地と道路の境界線を後退させること。
家を建てるときには接道義務によって4m幅以上(地域によっては6m幅以上)の道路に、敷地が2m以上接していなければなりません。
それを満たさないときには敷地を後退させて4m(中央線から2m)を確保するため、家を建てられる面積が小さくなる可能性があります。
Q:建ぺい率・容積率は変更できる?
原則として、不可です。
建ぺい率や容積率は、都市計画に基づいて用途地域ごとに自治体が定めているため、住民や建築主が勝手に変更することはできません。
前章で説明したように条件によっては緩和されるケースもありますが、個人レベルで変更できない点は覚えておきましょう。
まとめ
建ぺい率と容積率は注文住宅の建築面積と延床面積に大きく影響するため、土地探しの時点で必ず把握しておきたい指標のひとつです。
これらを見落としてしまうと、希望する広さの家を建てられない可能性があります。
理想の住まいを実現するためには、土地探しの段階から、住宅会社を決めておくことが大切です。
自分たちの希望と予算を伝えたうえで、それらを満たす土地の条件をアドバイスしてもらえば、失敗は防げます。
住宅会社探しの際にはぜひ、sumicaの「すまいの相性診断テスト」をご活用ください。
診断結果に応じておすすめできる複数の会社へ、一括で資料請求や相談の問い合わせができます。
(監修/(株)新潟家守舎)